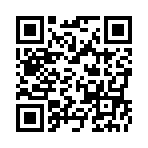2019年04月23日
風疹抗体検査結果・・・

今日は歯科受診が早く終わったので、近隣の医院に4月9日に採血した風疹抗体検査の結果を聞きに行きました。
《風疹の抗体価の判定(HI法)》
< 8倍 陰性
8倍、16倍:抗体価陽性(基準を満たさない)
32倍以上:抗体価陽性 (基準を満たす)
結果はHI法で64倍で十分抗体があるため、ワクチン接種は不要と。たぶん子供の頃にワクチンを打ったんじゃないですか?と医師から言われましたが、私の年齢だと下の表からいくと打ってないはずなんですが・・・。拍子抜けしましたが、まあワクチンも打たずに済んだので良かったと。ついでにPSA(前立腺腫瘍マーカー)も2年前と変わらず正常値でした。心配しすぎましたが、こればかりは結果論で、検査をしないと分かりませんので結果が良好で良かったです。これで大都市に胸を張って出かけます!予防接種を受けていない男性が、現在の感染を広げる要因になっており、特に問題となるのは妊娠初期の女性が、それが元で風疹に感染した場合に胎児に先天性風疹症候群を引き起こす可能性があることです。そのためにも他人事ではなく我々世代以上の男性は全員が交代検査は受けるべきでしょう。

《風疹の抗体価の判定(HI法)》
< 8倍 陰性
8倍、16倍:抗体価陽性(基準を満たさない)
32倍以上:抗体価陽性 (基準を満たす)
結果はHI法で64倍で十分抗体があるため、ワクチン接種は不要と。たぶん子供の頃にワクチンを打ったんじゃないですか?と医師から言われましたが、私の年齢だと下の表からいくと打ってないはずなんですが・・・。拍子抜けしましたが、まあワクチンも打たずに済んだので良かったと。ついでにPSA(前立腺腫瘍マーカー)も2年前と変わらず正常値でした。心配しすぎましたが、こればかりは結果論で、検査をしないと分かりませんので結果が良好で良かったです。これで大都市に胸を張って出かけます!予防接種を受けていない男性が、現在の感染を広げる要因になっており、特に問題となるのは妊娠初期の女性が、それが元で風疹に感染した場合に胎児に先天性風疹症候群を引き起こす可能性があることです。そのためにも他人事ではなく我々世代以上の男性は全員が交代検査は受けるべきでしょう。

2019年04月18日
薬剤師会講演会(心房細動に対する抗凝固薬の最近の動向)

本日は、JCHO桜が丘病院 院長 相川 竜一先生のご講演でした。
昨年より、新しく院長になられた先生ですが、循環器科が専門との事で、表記の演題について詳しく解説して頂けました。
抗凝固薬の話がメインで、ワーファリンとDOAC(直接経口抗凝固薬)の比較が主な話題でした。
多人種と比べると、アジア人ではワーファリンによる脳出血が多く、DOACの方が向いてるそうです。また、75歳を超えるとワーファリンのコントロールが難しくなるが、DOACに年齢の上限はなく、認知症・フレイル(高齢になることで筋力や精神面が衰える状態)が無ければ積極的に投与することが望ましいとの事でした。
専門医ならではの講演内容でしたが、DOACは添付文書に下記の【警告】の記載があり、副作用的に怖いイメージがあります。プラザキザだけには唯一、中和剤が発売されてますが他の薬剤にはありません。ワーファリンの方が簡易的にINR(プロトロンビン時間)を測定できるため、副作用面を考えるとフォローしやすい気がしますが、循環器の専門医からするとDOACの方が安全性が高いという意見になるようです。いずれにしろ、薬剤師としてできるのは、定期的な血液検査をしてるか?体重等の情報を元に適正に使用されてるか?他院の薬剤との併用確認等というところでしょうか。当薬局はDOACに触れる機会が多いため、薬剤の作用機序は分かりますが、専門医から直接的に薬剤の話を聞くことで勉強になりました。まだ、DOACの臨床データは少なく、今後のエビデンスを循環器医も待ちわびてるとの事だったので、それによって薬剤の使用法も変わってくるかもしれません。
DOAC添付文書より
【警告】本剤の投与により出血が発現し,重篤な出血の場合には,死亡に至るおそれがある.本剤の使用にあたっては,出血の危険性を考慮し,本剤投与の適否を慎重に判断すること.本剤による出血リスクを正確に評価できる指標は確立されておらず,本剤の抗凝固作用を中和する薬剤はないため,本剤投与中は,血液凝固に関する検査値のみならず,出血や貧血等の徴候を十分に観察すること.これらの徴候が認められた場合には,直ちに適切な処置を行うこと。

昨年より、新しく院長になられた先生ですが、循環器科が専門との事で、表記の演題について詳しく解説して頂けました。
抗凝固薬の話がメインで、ワーファリンとDOAC(直接経口抗凝固薬)の比較が主な話題でした。
多人種と比べると、アジア人ではワーファリンによる脳出血が多く、DOACの方が向いてるそうです。また、75歳を超えるとワーファリンのコントロールが難しくなるが、DOACに年齢の上限はなく、認知症・フレイル(高齢になることで筋力や精神面が衰える状態)が無ければ積極的に投与することが望ましいとの事でした。
専門医ならではの講演内容でしたが、DOACは添付文書に下記の【警告】の記載があり、副作用的に怖いイメージがあります。プラザキザだけには唯一、中和剤が発売されてますが他の薬剤にはありません。ワーファリンの方が簡易的にINR(プロトロンビン時間)を測定できるため、副作用面を考えるとフォローしやすい気がしますが、循環器の専門医からするとDOACの方が安全性が高いという意見になるようです。いずれにしろ、薬剤師としてできるのは、定期的な血液検査をしてるか?体重等の情報を元に適正に使用されてるか?他院の薬剤との併用確認等というところでしょうか。当薬局はDOACに触れる機会が多いため、薬剤の作用機序は分かりますが、専門医から直接的に薬剤の話を聞くことで勉強になりました。まだ、DOACの臨床データは少なく、今後のエビデンスを循環器医も待ちわびてるとの事だったので、それによって薬剤の使用法も変わってくるかもしれません。
DOAC添付文書より
【警告】本剤の投与により出血が発現し,重篤な出血の場合には,死亡に至るおそれがある.本剤の使用にあたっては,出血の危険性を考慮し,本剤投与の適否を慎重に判断すること.本剤による出血リスクを正確に評価できる指標は確立されておらず,本剤の抗凝固作用を中和する薬剤はないため,本剤投与中は,血液凝固に関する検査値のみならず,出血や貧血等の徴候を十分に観察すること.これらの徴候が認められた場合には,直ちに適切な処置を行うこと。

2019年04月16日
薬局の定期清掃

本日は専門の業者さんに入ってもらって窓や床をクリーニングしてもらいました。
朝、事務さんに今日、清掃業者さんが来ますと言われ、何!今日だったの?と。来月だと勘違いしてました。今日はレセコン業者さんの面談が夕方に入ってるので、清掃どころではなかったのですが何とか同時に終えました。
普段から毎日モップがけをしてるので、床は見た目は汚くはないんですが、ポリッシャーで洗浄すると汚い液体が出てくる出てくる。作業を見てるだけで何か楽しくなってきます。途中までは面白くて見ていたのですが、業者さんとの打ち合わせをしてる間にいつの間にか終わってました。床がピカピカになりましたが床に置いてあるパソコン本体を汚れないように机の上に上げるので、接続等でその後の作業が毎回大変ですが、年に1~2回の事なので仕方ありません。これで当面は気持ちよく仕事ができるでしょう。

朝、事務さんに今日、清掃業者さんが来ますと言われ、何!今日だったの?と。来月だと勘違いしてました。今日はレセコン業者さんの面談が夕方に入ってるので、清掃どころではなかったのですが何とか同時に終えました。
普段から毎日モップがけをしてるので、床は見た目は汚くはないんですが、ポリッシャーで洗浄すると汚い液体が出てくる出てくる。作業を見てるだけで何か楽しくなってきます。途中までは面白くて見ていたのですが、業者さんとの打ち合わせをしてる間にいつの間にか終わってました。床がピカピカになりましたが床に置いてあるパソコン本体を汚れないように机の上に上げるので、接続等でその後の作業が毎回大変ですが、年に1~2回の事なので仕方ありません。これで当面は気持ちよく仕事ができるでしょう。

2019年04月09日
風疹抗体検査

先日も下記のニュースが・・・
「4月2日、国立感染症研究所は2019年第12週(3月18日から3月24日)に全国で新たに74人の風疹患者が報告され、今年に入ってからの風疹累積患者報告数が1033人になったと発表しました。この時期に患者数が1000人を超えたのは、全国的に大流行した2013年以来です。」
4月に入り、予防接種の無料クーポン(昭和37年4月2日~昭和54年4月1日の間に生まれた男性が対象)が届きましたので、本日、近隣の医院を受診してきました。行けばワクチンを接種してくれるのかと思いきや、抗体検査をして抗体価が不十分な人だけワクチンを打てるようです。
問診表に、風疹にかかったことがあるか?MRワクチンもしくはMMRワクチンを打ったことがあるか?と記載されてましたが、親が覚えてないのに、私が分かるわけも覚えてるわけもなく 「分かりません」 と医師に答えたら、医師も 「私も(自分の事が)分からないんですけどね」 と和やかな会話になりました。
抗体検査は採血をするとの事だったので、ついでにPSA(前立腺がんマーカー)の測定もお願いしました。40歳を超してからは健康診断の際には自費でPSA検査を追加依頼してたのですが、最後に測定したのが2017年6月だったので、最近は頻尿も気になるので相談しました。先日のニュースで宮本亜門さんの前立腺がん判明の件が刺激になったのもありますが、、、。
結果は週末には出るとの事ですが、私は火曜日の夕方しか時間が空いてなく、かつ用事を常に入れてしまってるため、まあ焦らず空いてる時間に結果を聞きに行ければと思ってます。

「4月2日、国立感染症研究所は2019年第12週(3月18日から3月24日)に全国で新たに74人の風疹患者が報告され、今年に入ってからの風疹累積患者報告数が1033人になったと発表しました。この時期に患者数が1000人を超えたのは、全国的に大流行した2013年以来です。」
4月に入り、予防接種の無料クーポン(昭和37年4月2日~昭和54年4月1日の間に生まれた男性が対象)が届きましたので、本日、近隣の医院を受診してきました。行けばワクチンを接種してくれるのかと思いきや、抗体検査をして抗体価が不十分な人だけワクチンを打てるようです。
問診表に、風疹にかかったことがあるか?MRワクチンもしくはMMRワクチンを打ったことがあるか?と記載されてましたが、親が覚えてないのに、私が分かるわけも覚えてるわけもなく 「分かりません」 と医師に答えたら、医師も 「私も(自分の事が)分からないんですけどね」 と和やかな会話になりました。
抗体検査は採血をするとの事だったので、ついでにPSA(前立腺がんマーカー)の測定もお願いしました。40歳を超してからは健康診断の際には自費でPSA検査を追加依頼してたのですが、最後に測定したのが2017年6月だったので、最近は頻尿も気になるので相談しました。先日のニュースで宮本亜門さんの前立腺がん判明の件が刺激になったのもありますが、、、。
結果は週末には出るとの事ですが、私は火曜日の夕方しか時間が空いてなく、かつ用事を常に入れてしまってるため、まあ焦らず空いてる時間に結果を聞きに行ければと思ってます。

2019年04月03日
厚労省、非薬剤師でも可能な調剤業務を明示

厚生労働省は2019年4月2日付けで、「調剤業務のあり方について」の通知を都道府県などに発出しました。
薬剤師法第19条において、「医師、歯科医師又は獣医師が自己の処方箋により自ら調剤するときを除き、薬剤師以外の者が、販売又は授与の目的で調剤してはならない」と規定されていましたが、薬剤師の行う対人業務を充実させ、対物業務を効率化を図るため、今回初めて非薬剤師に実施させることが可能な業務の考え方が示されました。
内容をまとめると、
① 薬剤師の目が届く範囲内であれば、薬のピッキング、一包化した薬剤の数量の確認を薬剤師以外の者が実施することは差し支えない。
② 軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を直接計量、混合する行為は、 たとえ薬剤師による途中の確認行為があったとしても違法。
③ 納品された医薬品を調剤室内の棚に納める、調剤済みの薬剤を患者のお薬カレンダーや院内の配薬カート等へ入れる、医薬品の在庫がなく、卸売販売業者等から取り寄せた場合等に、先に服薬指導等を薬剤師が行った上で、患者の居宅等に調剤した薬剤を郵送等するのは、薬剤師以外の者が実施するのはOK。
なお、厚労省は、具体的な業務については情報通信技術(ICT)を活用するものも含め、有識者の意見を聴き、さらに整理を行い、別途通知するとの事です。いわゆるグレーゾーンを撤廃する形ですが、一包化の数のチェックもOKなのは驚きました。ダブルチェックという意味では良いとは思いますが。
アメリカでは薬剤師は医者や弁護士を抜いてもっとも信頼できる職業でとても高い地位にあります。上記のようなファーマシー・テクニシャンなどのいわば調剤助手がいて、薬剤師は服薬指導や相談に専念できる環境にいます。なぜなら、アメリカは国民皆保険ではなく、一部の金持ちだけが病院にかかれるため、それ以外の人は病院に行けず薬局に相談して薬を処方してもらうため薬剤師が医師の代わりになってるからです。国民皆保険の日本においては、まったくそれは当てはまらないわけで薬剤師は微妙な立場に常にいます。
日本薬剤師会は今回も反発すると思いますが、弱いので直に押し切られる気がします。そして、チェーン薬局の上層部はこの案を大歓迎するしょう。ただ、ファーマシー・テクニシャンも薬剤師と連携できる資質・資格は必要だと思うので、すぐにはならないとは思いますが・・・。今年も第104回薬剤師国家試験の合格発表があり、合格率70.91%、約1万人の薬剤師が誕生しました。年代が上がるほど悲観的な薬局業界と言われてますが、これからは多彩な認定取得、地域貢献、長時間勤務の薬剤師だけが生き残る?ような競争の時代になっていきます。
そのため、① 研修会等に常に参加し研鑽していく ② 健康に留意ししっかり仕事をする ③ 家族を大事にする、そして今を全力で生きていきたいと思います。

薬剤師法第19条において、「医師、歯科医師又は獣医師が自己の処方箋により自ら調剤するときを除き、薬剤師以外の者が、販売又は授与の目的で調剤してはならない」と規定されていましたが、薬剤師の行う対人業務を充実させ、対物業務を効率化を図るため、今回初めて非薬剤師に実施させることが可能な業務の考え方が示されました。
内容をまとめると、
① 薬剤師の目が届く範囲内であれば、薬のピッキング、一包化した薬剤の数量の確認を薬剤師以外の者が実施することは差し支えない。
② 軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を直接計量、混合する行為は、 たとえ薬剤師による途中の確認行為があったとしても違法。
③ 納品された医薬品を調剤室内の棚に納める、調剤済みの薬剤を患者のお薬カレンダーや院内の配薬カート等へ入れる、医薬品の在庫がなく、卸売販売業者等から取り寄せた場合等に、先に服薬指導等を薬剤師が行った上で、患者の居宅等に調剤した薬剤を郵送等するのは、薬剤師以外の者が実施するのはOK。
なお、厚労省は、具体的な業務については情報通信技術(ICT)を活用するものも含め、有識者の意見を聴き、さらに整理を行い、別途通知するとの事です。いわゆるグレーゾーンを撤廃する形ですが、一包化の数のチェックもOKなのは驚きました。ダブルチェックという意味では良いとは思いますが。
アメリカでは薬剤師は医者や弁護士を抜いてもっとも信頼できる職業でとても高い地位にあります。上記のようなファーマシー・テクニシャンなどのいわば調剤助手がいて、薬剤師は服薬指導や相談に専念できる環境にいます。なぜなら、アメリカは国民皆保険ではなく、一部の金持ちだけが病院にかかれるため、それ以外の人は病院に行けず薬局に相談して薬を処方してもらうため薬剤師が医師の代わりになってるからです。国民皆保険の日本においては、まったくそれは当てはまらないわけで薬剤師は微妙な立場に常にいます。
日本薬剤師会は今回も反発すると思いますが、弱いので直に押し切られる気がします。そして、チェーン薬局の上層部はこの案を大歓迎するしょう。ただ、ファーマシー・テクニシャンも薬剤師と連携できる資質・資格は必要だと思うので、すぐにはならないとは思いますが・・・。今年も第104回薬剤師国家試験の合格発表があり、合格率70.91%、約1万人の薬剤師が誕生しました。年代が上がるほど悲観的な薬局業界と言われてますが、これからは多彩な認定取得、地域貢献、長時間勤務の薬剤師だけが生き残る?ような競争の時代になっていきます。
そのため、① 研修会等に常に参加し研鑽していく ② 健康に留意ししっかり仕事をする ③ 家族を大事にする、そして今を全力で生きていきたいと思います。